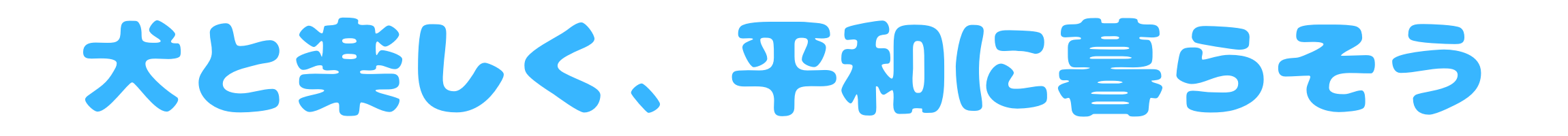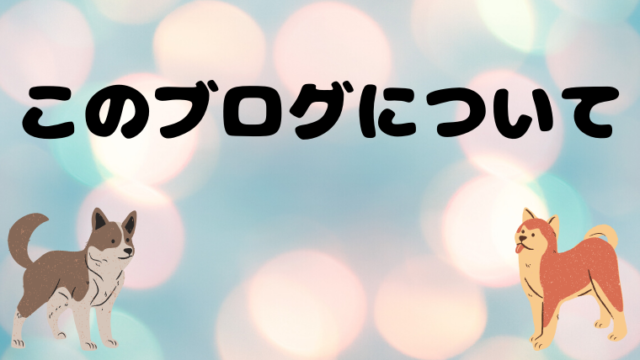急なストレスを減らしたい!犬に予測可能性を提供してQOLを上げたい
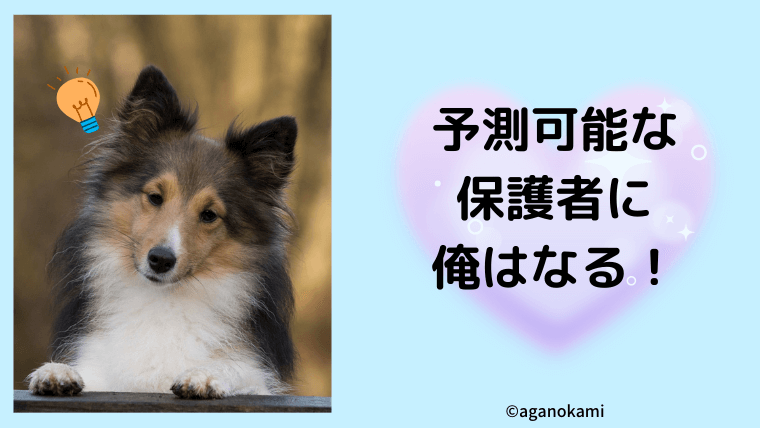
いつもご観覧いただきありがとうございます。今回は予測可能性について書こうと思います。
ストレスには様々なものがありますが、
今回のお話でいう急なストレスとは、予測がつかなくてびっくりする様な事や、予期せぬ嫌な出来事です。
予測がつかない事のストレスを減らしたい

私たち人間も、予測がつかない事があると凄くストレスを感じますよね。例えば…
- 新しい職場や学校でどう振る舞えばいいのか、全然わからん
- 忙しいのに急な予定変更に振り回される
- 突然の大きい音や光、衝撃
- 予想外のミス、事故、災害など
私達は人生を経験していくうちにこういう物事に備える事もでき、備えあれば憂いなしという状態に可能な限り近づく事ができます。
経験は大事とはいえ、一つ一つをガツンガツンと大怪我を受けながら経験するよりも、周りの方々から先人達の知恵を教えて貰い安心感のある中で経験していくのが良いですよね。
何も知らされないでチャレンジさせられ、出来なかったら叱られたり評価が下がったり怪我をするかもしれないのは物凄いストレスじゃないですか?
前もって色々教えてもらってある程度予測可能になっていたら失敗が減りますし、もし失敗しても大ダメージになりにくいので回復が速いと思います。
回復が速い分、次はこうしよう!みたいな改善策も、大ダメージを受けた時よりも素早く練る事ができて安心感にたどり着くのが早くなります。
経験する機会は向こうから来ます。きたる経験に備えて、憂いなしの状態にしておきたい!
私たち人間でも、せわしない人間社会に参っているのですから、そこで一緒に暮らしてくれている犬は相当がんばってくれているなと思います。
なので今回のお話は、犬が受けるであろう数あるストレスの中から【予測がつかない物事】を減らしてどうって事ないね、を増やしていこうという試みです。
ポジティブな予測がつく事は幸せ

私たちも、少し頑張ったら良い結果になるだろうと予測がつくとやる気になりますし、なんでもない事と予測がつけばリラックスしていられます。
悪い結果になる事が予測できれば自分の行動を変える事もできるし、悪い結果が避けられないと予測がつけば憂鬱になりますね。
この脳の仕組みは生き物によってあまり違いがありません。
- どんな動物の脳もパターンを見つける様にできている
- これは生存に不可欠なスキル。パターンがあれば世界はより予測しやすくなり、動物の労力を節約できる
Kim Brophey CDBC, CPDT-KA. Applied Ethologist and Owner of The Dog Door Behavior Center
- 犬も人間と同じ様に予測可能性を求めている
Ken Ramirez Executive Vice President and Chief Training Officer of Karen Pryor Clicker Training
私はこのお二人↑大好きです。今後もこういう方々から学んでいきたい!
- 不安やストレスを減らす
- 信頼関係や自信を育む
- トレーニングがより効果的になる
つまり犬にとって良い結果の予測可能性は安心感を得たり・QOLが向上したり・精神的な回復力を育てる事に役立ちます。
そして予測不可能性と避けられない嫌悪刺激(悪い結果)の予測可能性はストレスにつながり、不安や恐怖による反応がある場合はより反応が強くなる可能性があるそうです。
昔から犬には一貫した態度を、と言われるのはこのためかなと思います。
人間にも一貫した態度がいいなあ、気分で態度が変わる人と仕事をしたり、職場のルールがころころ変わるのはストレスですよね
<PR>
予測可能性の高い保護者になる為にできる事

一貫した態度とは具体的にどうすればいいのか?できる事はたくさんあります。
- 強制トレーニングや嫌悪刺激を使うトレーニングをやめる▶︎強制的だったり嫌悪刺激を使うトレーニングでは、予測不可能な嫌悪刺激による苦しみ、嫌悪刺激から逃げられない事が予測できるため慢性的にストレスフルになる
- ポジティブトレーニングに切り替える▶︎スモールステップによる予測可能なキュー(合図)、予測可能な強化子
- お手入れ以外にもCooporative Care トレーニング(ハズバンダリートレーニング)なやり取りを取り入れる▶︎新しい物事を急に・強制的に行わず、安心感のなかでゆっくり紹介
- 無理のないルーティーン▶︎保護者であるかいぬしさんが無理をしない=余裕があって急な変更が少ない
- かいぬしさんが予測可能な存在になる▶︎お終いの合図など、物事の前に合図を出す・大声で叱ったりリードショックや天罰法などを行わない
- 犬が何歳でも社会化をサポートする▶︎予測可能な物事を増やす
ポジティブトレーニングに切り替えたい・Cooporative Care トレーニングを教わりたいならR+LINKSで嫌悪刺激を使わないトレーナーやグルーミングサロンを探す事ができます。
生活のルーティーンが決まっている事は良いと言われていますが、季節によって散歩できる時間が変わったり仕事の都合がはさまったりと、どうしても変動しますよね。
なのでルーティーンに関してはあまりに無理して固定するものでもないかなと思います。私は季節で散歩の時間をずらす時は気温にあわせて少しずつずらしてます。
社会化についてはこちらをどうぞ↓

普段の生活の中で簡単にできる事をいくつか紹介しようと思います↓
リーシュでコントロールをやめて合図を作る
お外にいる時に、こっちに寄って欲しい・今はそっちに行けないよといった状況がありますよね。
そんな時に、急にリーシュを引っ張ってコントロールする事をやめて、代わりに合図を作る事ができます。
ちっちっちと舌を鳴らして来てもらう
名前やおいでのキューで来てもらう
ハンドターゲットで誘導させてもらう
これらの合図は強化子がもらえる様にします。強化子はその子が欲しいものならなんでもいいですが、犬の「あっちに行きたい」などを諦めてもらうのでその価値に見合ったものならやはり食べ物が嬉しいのかなと思います。
犬が行きたい方向へ行く時などは、それ自体が強化子になると思います。
お終いやないないの合図を作る
トレーニングや遊びが終わった時や、何かを食べ終わった時などに「もう終わったよ」の合図を作る事ができます。
犬が終わりの合図を知る事で、「もっとやる!?もっとくれる!?どうすればくれるの!?なんでくれないの!?」といった予測不可能なフラストレーションを減らして「もう自由時間だな、休もうかな」と次の行動を選択するのに役立ちます。
トレーニングや遊びの後、「おしまい」と言って小さいトリーツをいくつか投げる▶︎犬は楽しく鼻や目を使ってトリーツ探しをして一息つく
おやつを食べた後やお裾分けをした後、「もうないないよ」と言って手をひらひらして見せる
犬が食べられないものを欲しがった時に「ないないよ」と言って手をひらひらして見せる
もちろん「おしまい」や「ないない」はどんな単語でもいいし、手をひらひらの代わりに別の動きでも大丈夫です。使いやすいものを合図にする事ができます。
私が使っている「ないない」の両手ひらひらは、柳沢慎吾のパトカーの動きに似ています(わかる世代はわかる)
ブラッシングや爪切りの終わりも「おしまい」とトリーツが来るわん
「ないない」って言われたら、ないものはないわんよ、休憩するわん
体に触る時の合図を作る
社会化の中でも体のどこを触られても平気にしましょうと言われますよね。でもいきなり後ろから触られたり、いきなり抱っこされたりするのは私たちもびっくりするし嫌ですね。
抱っこする前に「抱っこ」と言う
いまから撫でるよ、が犬にわかるように手のひらを見せたり、「なでなで」と言う
体を触る時には犬に見える位置から、「こっちの耳」とか「お口」とか触る場所を言ってから手を伸ばす
お手入れなどで体に触る前触れとして「チンレスト」を教える
散歩終わりに足を拭く時は「こっちの足」と言ってその足を触ってから持ち上げる
チンレストはCooporative Careでもよく使われています。
体に触られるケアの前触れとしてだけでなく、犬がチンレストをやめた時には「もうやめる」や「ちょっと待って」の私たちへの合図としても機能します。▶︎嫌悪刺激を使わないトレーナーに貰えます。グルーミングに取り入れているサロンもあります。
足を拭く時の「こっちの足」は靴を履く時にも使えます。
急に足を持ち上げると体重の移行がついていけず、ガクンとなってしまったり、脚だけでなく背骨や腰なども痛めてしまうかもしれません。
持ち上げられる足の予測がつくと、事前に力を抜く事ができて身体を痛める可能性を減らす事ができます。
こっちの足〜って触られたら、その足を軽くして他の3本に体重を移すわんよ
ほかにも、うちの子が予測がつかなくて困っている事はなんだろう?どんな時にフラストレーションを感じているだろうか?と観察していると、必要な合図が見えてくると思います。
気をつけたい事
以下は特に「ないない」の合図を教える時に心にとめておきたい事です。
いつも「ないない」ばかりだとフェアじゃないし、こちらも心が痛みます。
犬が「今回はないないだけど、他にも楽しいと美味しいがたくさんあるもんね〜!まあいっか」と思える様に、たくさんのエンリッチメントを提供したいですね。
「ないない」を聞いてもらうなら、日常的に満足度の高い生活を送れる様に犬満たししていきましょう。
パピーには安心安全感とこの人がお世話してくれるんだ!という確信を持ってもらうのが先です。特にパピーライセンスが切れていない月齢には「ないない」より叶えてあげる事を優先しましょう。
パピーが何かを求めてくると言う事は、何かが足りていない可能性の方が高いからです。▶︎お世話、お遊び、お甘えetc
そして、合図は命令(コマンド)ではないという事。
私たちは犬を従わせて完璧にコントロールしたい訳ではないんだな〜。このブログに来てくださっている方は、そういう仲間だと思います。
社会的な生き物が共に繁栄する為には、公平さ▶︎お互いにNOと言えること、共感▶︎お互いのNOを受け入れること、協力▶︎Cooporative Careな取り組みが鍵です。
犬のNOを尊重するやり取りができる様になるためには、ボディランゲージを知る必要があります。

予測可能性を育んでより良い暮らしを
事前にわかりやすい合図を出す事はかいぬしさんが予測可能性の高い、より安心感のある保護者になるために役立ちます。
予測可能性の高い保護者になって、さらに犬のNOも聞ける様になれば、犬とお互い様なやり取りができて信頼貯金が溜まっていきます。
犬は自信を育んで精神的な回復力もレベルアップしていきますし、信頼貯金の残高が高い=いざという時の呼び戻しなどに協力してもらえる関係になれるので、犬の命を守る事にも繋がります。
そんな感じで、今回は予測可能性について書いてみました。
それでは、よい犬暮らしを!