叱らない犬育てでできる引っ張らないお散歩経過報告
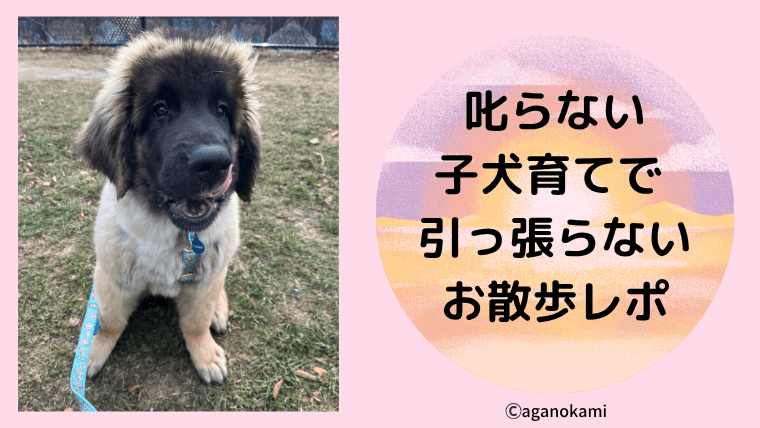
いつもご観覧いただきありがとうございます!菊ちゃんは現在1歳前後で、引っ張らないお散歩がとってもお上手です。
超大型犬でハーネスで引っ張らないで歩くって、どうやって教えたん?
基本的には人間のリーシュテクニックと、リーシュでコントロールしようとしない事です
どんな風に取り組んできたのか、今まで勉強してきた事と経験をまとめてみようと思います。
先代楓と同様、ゆるウォークをしていく!

ゆるウォークお散歩形式
- リーシュの範囲内で前、横、どこを歩いても自由
- 安全な場所・迷惑にならない場所での匂い嗅ぎや観察、休憩に付き合う
- 安全な限り犬に連れてってもらう
- 混んでいる道や他者が近くに来た時など、限定的に近くに来てもらうか私が犬の横に行って壁になる
- 犬の自力判断を阻害しない長めのリーシュと快適なYH型ハーネス
犬のニーズを満たして安全な範囲で活き活きと暮らしてほしいので、この様なお散歩をしています。
かいぬしが安全基地になり叱責や首が締まる心配もなくいざとなったら間に入ったりして助けてくれるという安心感が大切です▶︎安定型の愛着を目指しています。
安定型愛着というしっかりした土台の上で、安心安全感を感じながら自分で判断して学ぶ事ができると、犬自身もより安全な行動を選ぶ事ができる様になっていくので、トレーニングは最小限に抑えられ、成長を楽しむ事もできて凄く幸せです。
ゆるウォークでしない事・する事
犬との上下や主従を作るための散歩や、犬を統率して導く散歩という考えは採用していません。
それらは犬が選択肢なく付き合ってくれているから出来ている様に見えるだけで、
相手の選択肢を狭める事によって上下主従を作ったり統率して導いたりする事は、種を越えて実際にはできません。
私の役割は、勝手に動くな・匂いを嗅ぐな・まっすぐ横を歩け・座れなどのコレクションや指示を出して相手をコントロールする事ではなく、周囲に目を光らせて安全を確保し犬のニーズを満たす環境を設定する事と、犬が困ったら手助けする事です。
お散歩関連の記事はこちらもどうぞ▼

超大型犬でもハーネスでも引っ張らないお散歩はできる

バーニーズでもレオンベルガーでも
さて故・楓はバーニーズ、菊はレオンベルガーですが、ハーネスで引っ張らないスタイルです。
楓は私が犬勉強のスタートラインにいた事もあり、1歳半くらい?まではなかなか大変だったと思います。他国だし食べ物のゴミが落ちまくっていたりパリピ御用達の騒がしい通りがあったりリスが多いなど、地域がクセ強で私が混乱していました。
それでも通ったパピー教室がポジティブトレーニングだったし嫌悪刺激使いたくないな〜と思って勉強を始めたので、のちのちはかなり楽に楽しくお散歩できました。
ポジティブトレーニングと言うと「楽な犬を一頭二頭しつけたところで」とか「あなたの犬は楽な犬だからポジティブでもやれただけ」などと言われますが、楓も菊も「楽な犬」ではないです。どの犬も犬なりにヒトにとって大変なところがあると思いますよ。
二頭とも、もしバランスドトレーニング(英語圏で言う褒める+叱るのトレーニング)に通っていたら「主張が激しい」などとレッテルを貼られ叱られたりスリップリーシュで圧迫されていただろうな、と思う瞬間がいくつもあります。
「従わせないといけない」というメガネを通して見れば、二頭とも自立心がしっかりしており決して従順ではないので「かいぬしを無視してもいいと思っているので意識を向けさせるために首に合図を出す」と言われたり、こちらが力を使えば倍以上の力で抵抗できるので「子犬のうちに厳しくしないと大変な事になりますよ」とチェーンやプロングを使う様に言われたかもしれません。
菊は楓のお陰で私も学んだので、最初から引っ張らないお散歩ができています。
えっへん!これからも励むわんよ〜
かえちゃんありがとう!
ふたりとも、リーシュが張ったとしてもギューっと引っ張る事はなくこちらの腕がふわふわっと上がる程度です。
んでリーシュが張るとよほど脅威や興味のある物に目を奪われていなければ、大抵歩をゆるめたりして協力してくれます。助かる。
もしも脅威に目を奪われたなら、私が間に入って遠くへ連れ出す時です。
なので私は引きずられたりぶっ飛ばされたりした事がありません。
トレーニングで教えた事・維持している事
安全に外を楽しむために、これだけ覚えて貰いました↓都会なので覚える事が多いですが…
- 曲がり角に来たら先に行かないor止まってください(鉢合わせ防止)
- すれ違う時は私の横or壁際を歩いてください
- ハンドタッチ
- 呼び戻しキュー、緊急リコール(拾い食い防止としても)
- drop it
- 横断歩道でのステイ
- ドアが開いたら待ってください
すべて正の強化でかなり簡単に教えられます。人間は継続が苦手なので維持していくのが難しいのかな。
楓が劇的に引っ張らなくなった時にした事

変えた事
- リーシュを長めのものに変え、リーシュで圧をかけない扱いを勉強した
- 前脚が拘束されないハーネスに変えた
- 安全ならとにかく待つ
- 散歩中に休憩や匂い嗅ぎや宝探しなど、楓がやりたい事にもっと付き合う
楓はクリッカートレーニングのパピー教室に通いましたが、それだけではまだまだ知識が足りませんでした。メンドクサイ思春期(犬も人間も!笑)の対応や種としてのニーズなども知らずだったし、拾い食い防止のためにマズルを使いましたが舌が届いてしまうのでハルティ(ジェントルリーダーみたいなやつで、スリップリーシュよりも絞まらないタイプ)を使ったりもしました。
楓が思春期の敏感な頃、引っ張るわけではないのですがあまりに俊敏にわちゃわちゃしていて、話しかけられると興奮するので近所の方からADHDじゃない?と言われ、ご迷惑をおかけしてはいけないと思いイージーウォークハーネスを使った期間もあります。
ご近所迷惑にならない様にと痛みや圧迫のある犬具を選んでしまう気持ち、凄くわかります…この犬具を使っている=トレーニング中なので話しかけないでください!という気持ちもありますよね
今はイエローリボンも広まってきているので、そちらがおすすめ!
勉強していくと、どうもリーシュが短すぎる+犬具が拘束的で不快感があるために精神的な余裕がなく、落ち着いていられないのでは?という疑問が出てきました。
そこで1.5mリーシュから1.8mリーシュに変えてイージーウォークハーネスを辞めたところ、劇的に落ち着いたのでした。たった30cm違うだけで、こんなに違うんだと思いました。
こういう持ち手が柔らかいタイプが個人的に使いやすいです。反射材が縫い込まれているのがいいですね。3mリーシュが使える土地ならユリウスのグリップのやつか、メンドータがいいと思います。
匂い嗅ぎや休憩などのアクティビティ、何かを情報処理する時間など、もっとゆったりと私が落ち着いて付き合う様にしました。
そうしていくとどんどん落ち着いていったし、楓の動きもゆっくりになってボディランゲージもよく見える様になりました。
もっとはやく知っていたら良かった…楓を混乱させて辛い思いをさせてしまっていました。反省。
菊お散歩デビュー後パピー初期

楓に教えてもらった事をふまえて、菊とのお散歩はこんな風にスタートしました。
とりくみ
- 安心安全を感じてもらうための社会化のサポート
- YH型ハーネスと2mリーシュ
- 自由運動ができる場所ではロングリーシュ
- 安全の範囲でリーシュが張らない様についていく
- リーシュの圧がかからない様にする
- 短時間を1日2回ほど、超距離は歩かせられないので芝生へカートで
とにかく安心安全、安定型の愛着(簡単に言うと絆?)、ムリのない体の使い方、匂いを嗅いだり距離を取ったりして落ち着ける事を学んで、リーシュがついている時も拘束されているのではなく発言権選択権がある事を知って自信をつけてもらいたい。
社会化についてはこちらもどうぞ▼

体を壊さない為にもリーシュでコントロールしない
骨格や神経系、軟部組織の発達のためにも、リーシュコントロールによって体に圧をかけない事がとても大切です。
特に超大型犬の子犬は成長しきらないうちに骨格に無理をさせてはいけません。リーシュで引いて長距離歩かせるのは厳禁です。
短いリーシュだと匂いを嗅ぐだけですぐに張ってしまい、子犬の身体が斜めに湾曲したりガツんと圧がかかって関節や筋膜を痛める可能性があります。
またリーシュコントロールによる圧が不快感や身体の痛みや不安を与え、それが周りにあるものとペアリングしてしまい(古典的条件づけ)社会化の妨げになったり後々激しい行動の原因になってしまいます。安心感を育てたいのに意図せず逆の結果を招いてしまうわけです。
止める必要がある時は呼び戻しキューを使うか、リーシュをガツんと引かずに、脇を閉めて手を固定して柔らかく止めます。
長めのリーシュで土や芝生の地面を自由に探索してもらい、リーシュが張らない様についていきます。子犬は自発的にちょっと走ったり止まったり寝転がったりするので、私も走ってついていきます。子犬が休んでもリーシュを上に引いて立たせてはいけません。
子犬の走りなんてほんのちょっとです。らくらくよ。
子犬は自由に匂いを嗅ぐ事で自然な頭の上げ下げをして、健全に体を発達させる事ができるので、嗅いでも大丈夫なものか私が素早くチェックできる様にするためにも、子犬についていきます。
ヒトには犬を小さいうちから自由にさせて引っ張る様になったらどうしようという焦りもあるものです。
生き物は体のバランスを保つために引っ張られると引っ張り返す、押されたら押し返す本能を持っています(もちろん人間も)から、こちらがリーシュを引いてばかりいると犬はリーシュは引かれるものだから倒れない様に引き返さなきゃ、となるわけです。
リーシュがついている時=引く・引き返すのが当たり前の時という風に学んで欲しくないんですよね。リーシュを引いて欲しくないのでまずは私から、リーシュを引かない事です。
協調性は犬を犬として犬らしくサポートして育てていると自然とついてくるもの、なにせ相手は社会的動物の中でもコミュニケーションのエキスパートですから。
菊思春期のお散歩での積み重ね

生後5〜6ヶ月からはパピーライセンスも失効して思春期!ヒトも犬もいよいよめんどくさい時期です(笑)
とりくみ
- パピー時のとりくみを継続する
- 様々な刺激に敏感になる時期なのでサポートする
- 成長期のアンバランスさによる体の不和などが生じる事を念頭におく
- 歩く時間は30分くらいまでを2回、あとは環境観察などゆっくり過ごす
- 助けたらどうだったか、時間を提供したらどうだったか、記録をとる
リーシュを引かない事などを継続しつつ、大人への階段をできるだけすんなり登れる様にサポートしたい。
思春期の犬によくある誤解
この時期は脳と身体の成長に伴って今までになかった行動が出てきますが、それが「反抗している・主張が強くなった」と勘違いされリーシュでくいくいされる服従訓練などをされて更に身体を痛め、その痛みや不快感によって激しい行動が出るという悪循環にハマりがちです。
特にお座りをためらったりしなくなったりするのは後ろ足が長くなっていて、脚・腰・背骨などに痛みや不快感があるためで、「かいぬしを無視しようとしている・反抗している」のではありません。
小走りや早足で歩きがちになるのも、後ろ足が長くアンバランスで体の背面に負担がかかっているために速度を落とす事ができない可能性があります。「かいぬしよりも前を歩きたがるドミナント、犬がリーダーになろうとしている」のではありません。
安全な限りはリーシュが張らない様に犬の早足に着いて行ってましたが、1歳前後の今は早足になることが減り、相変わらず引っ張りも出ていません。
今は芝生でだけちょっと走ろう!って誘ってきます。
お座りの体への負担についてはこちらの記事もどうぞ↓

かいぬしの声が届きにくくなるのはより多くの刺激に敏感になり、脳が情報を処理しようとフル回転しているからで、「かいぬしを無視してもいいんだと学んだ・わがままになってきた」のではありません。ちょっと今は声が届かない時期かもな、と念頭に置いて環境を選びましょう。
成長痛・骨格のアンバランスさによる不快感・皮膚感覚も敏感になるため家の中でも、撫でられる事を避けたり肩や背を撫でたら突発的に口を当てたりする場合があり、わがまま・反抗的と勘違いされがち。あーしまった、触られたくなかったね、ごめんねって思う。
この時期は小型犬の方が短いとされています。超大型犬ならより長いでしょう。
大変かもしれないけど、外の世界で軽犯罪に巻き込まれたりする人間の思春期より断然楽だよ。
成長期でいろんな行動がでてくるだけわんよ
体も大きくなりパピーライセンスも失効するためか、少し年上の血気盛んな犬から吠えられる事も増えますし、距離や相手によっては側に寄って調べたくてダッシュしたがる事もあると思います。思春期にリスクを取る様な行動が増えるのは人間と同じですね。
その時に間に立ってあげたらどうだったか、横にいて一緒に観察したらどうだったか、距離や環境なども一緒に記録していき、菊ちゃんにとって一番良さげな対処を割り出していきます。危険手当として吠えられボーナストリーツを食べる事も。
今の所菊ちゃんは広い公園では匂いを嗅いでスルーしたり、座ったり伏せたり体を背けて距離を取ったりといったカーミングシグナルを見せますが、家の前の狭い芝生だと緊張して動けなくなる時もあり、その時は間に立ってあげると少し体が柔らかくなります。その間に通り抜けて貰います。▶︎犬にとって距離やスペースが重要である事がよくわかりますね。
より他の犬が残した匂いにも敏感になるので、時々その道は行きたくないというそぶりが出る事もあります。前にその道を通った犬に何かネガティブな事が起こり(吠えられたとか叱られたとか)、その犬が残したコルチゾール等が含まれる尿や足の裏の情報からストレスや不安を感知している可能性があるとか。
そういった人間にはわからない事情があるので、道は安全の範囲で菊ちゃんに選んでもらってます。
どうしてもその道には行けないよという場合は、菊ちゃんの視界に入って体を別の道の方へ傾けたり指を指したりして、ボディランゲージで「こっちの道はどう?」と提案します。
向こうから吠える犬が来たり渋滞発生で緊急で曲がらないといけない時などは呼び戻しキューやハンドタッチを使ってありがトリーツです。
そんな取り組みを続けてきてそろそろ1歳になりますが、ひっぱりはありません
実は引っ張らないトレーニングはしていない

ここまで読んでいただいておや!?と思った事がありますよね?
そうなんです、「ツイテ」や「前に出てはいけない」などのトレーニングは全然してませんのです。でも引っ張らないで平和に歩く事ができています。
外でやるトレーニングっぽいことと言えばこれくらい↓
トレーニングと遊び
- ハンドタッチや宝探し
- 拾い食い防止や他所様にご迷惑をかけないための呼び戻しキューと緊急リコールの練習
- drop itの練習
- 信号待ちのステイ
- すれ違いや曲がり角で協力してくれたらありがトリーツ
うちは人口の多い都市型環境なのでこのくらいのトレーニングは必要になりますが、郊外や田舎ならそんなにがんばらなくても大丈夫かなと思います。
私の地元だとすれ違い皆無、信号も無い、曲がり角は向こうが見えてるのでね…
ずっとトレーニングして歩いているのではなく、犬が犬として学ぶ事に重点を置いていると自信がついて穏やかになってゆくので、徐々にキューを使って犬に頼み事をする事自体が少なくなっていきます。
トリーツの使用頻度も自然と減っていき、胃捻転や胃拡張が心配になるほどの量は食べていません。
嫌悪刺激やリーシュコントロールの圧を用いてのトレーニングは予後が悪くなる可能性があるのと、犬が辛い思いをする事はやりたくないので採用していません。
アイコンタクトやリーダーウォークなどの服従訓練を、嫌悪刺激やリーシュ圧を用いて強制的に行う事は体の故障の原因になりますし、必要ないのでしていません。
嫌悪刺激を用いてのトレーニングは、ブリーダーさんとの契約違反でもあります。
犬の自然な、匂いを嗅いだりしながら歩いたり自分で考えてカーミングシグナルを出したりする事を封じ込めてまで楽な散歩をしたくありませんし、犬にも安全のために周りを見て欲しいのでアイコンタクトを求める気持ちはないです。
アイコンタクトを歩きながらさせる事は犬の首にとって不自然な角度なため、首や肩に負担がかかりますが、実は私も首が痛くて。
周りの安全や地面に変なものが落ちていないかを確認しながらボディランゲージも見て忙しいので、真横をリーダーウォークしている犬とアイコンタクトをするために頭を横下に向けるよりも、頭は前を向いていて全体を見れる方が助かります。
もちろん、犬が見たい時に見てくれるアイコンタクトは嬉しいし応えますよ!私から犬にアイコンタクトせえ!と求める事は無いってだけですの。
過度なコントロールはせっかく犬と暮らせてるのに勿体無いって思います。
犬という種を一番近くで見せて欲しいんであって、ロボットや舎弟の様に従って欲しいのではないんです。
自分の子供の頃を思い返せば、教師に「授業で手を上げないと罰を与える」と脅されて習わされる事よりも、自分で面白がって読んだ本の内容の方がよく覚えています。
タフラブの小学校担任の時は毎日叩かれたり叱責されたり罰としてグラウンドを走らされる不安で授業の内容は定着せず、嫌悪感しか残っていません。同じ教育費を払って隣のクラスは教科書が進んでいるのにうちのクラスは教師の不機嫌による授業放棄などで授業も進まず、損をさせられました。もったいない!!
犬も自ら犬として学ぶ方が安全に歩けるのではないかと考えています。より犬にとって有益な自然な学びをしてもらうにはどうすればいいか?を勉強していきたい!
トレーニングしすぎにならない様にとは言っても、トラブル対処などを人道的に行うには行動の知識が必要なので、ABAを用いたトレーニングの方法を学ぶ事はスキップできないと感じています。
お散歩に役立つ事を学んだおすすめ本などの一部を紹介します↓
参考書など
日本のしつけ本はカナダから買うと高いし、今の所ポジティブトレーニングで痒い所に手が届くものがあまりない様に思うので、英語圏のものを参考にしています。
言わずと知れたトゥリド・ルーガス先生の良書。基本はこれでええやん!となります。
拾い食い問題をポジティブトレーニングで。これは本当に買って良かった!目から鱗の内容。特にどう立ち回ったらよいかの図解がわかりやすくて良かったです。
強固な呼び戻しをポジティブトレーニングで。厳しく教える必要なんてどこにもない!
https://school.grishastewart.com/courses/handouts
私が今勉強しているBATの無料資料。日本語版あり。人間のリーシュスキルなど。
https://school.grishastewart.com/courses/leash-walking
長いリーシュの持ち方やお散歩中にできるゲームテクニックを動画で。短い動画がたくさんで少しずつ学ぶ事ができて良いです。
なぜパピー〜成長期の犬にリーシュを張る事や強制的な服従訓練をおすすめできないのか、身体の仕組みや発達を知る事で理解できる本です。
またパピー〜成長期にどの様な運動をすれば健全で強い肉体を目指せるか、写真つきで細かく載っていて本当におすすめ!
そんな感じで今回は叱らない犬育てで引っ張らないお散歩について書いてみました。引き続き楽しく勉強していきます!
それでは、よい犬暮らしを!
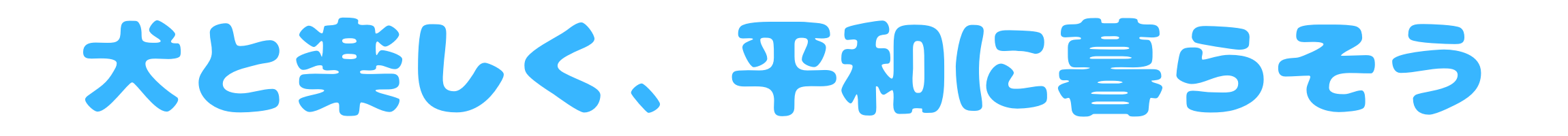

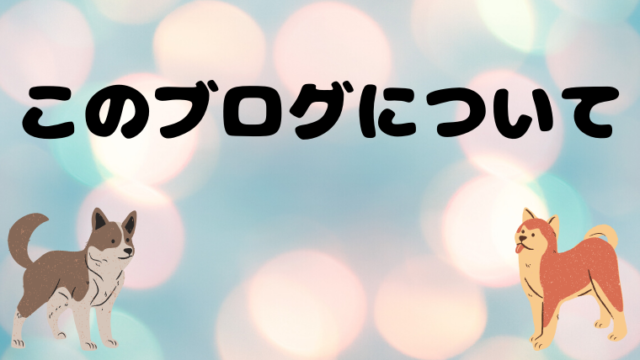







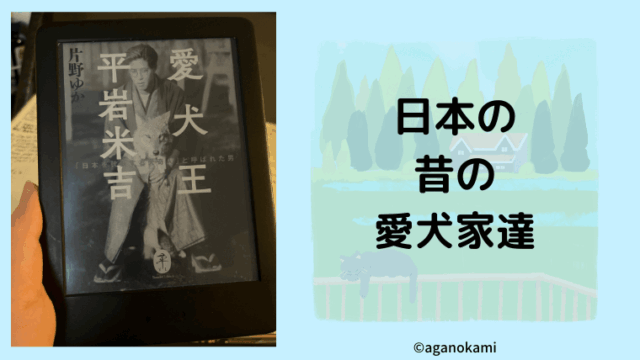

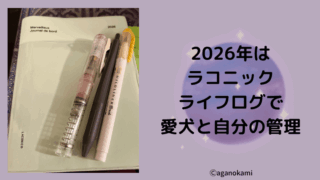
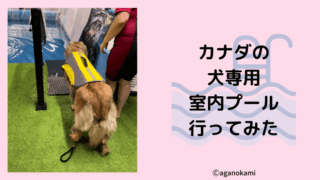


リーシュスキルや拾い食いについては、この記事の最後に参考にしたものや本やウェブサイトなどの情報を載せていますのでそちらをご覧ください